将来の資産形成の手段として注目されている「iDeCo(イデコ)」。私も将来に向けた節税と老後資金の準備のために、SBI証券でiDeCoを始めました。
この記事では、実際に私がiDeCo口座を開設した流れや、手続き中に遭遇した注意点などを、初心者でも分かりやすいようにまとめました。
iDeCoを始めようか悩んでいる方、SBI証券での始め方を具体的に知りたい方に向けた実践ガイドです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?
iDeCoとは、自分で掛け金を拠出し、運用しながら老後資金を積み立てていく年金制度です。最大の特徴は節税メリットにあります。
- 毎月の掛け金が全額「所得控除」の対象になる
- 運用益が非課税
- 受け取り時にも「退職所得控除」や「公的年金等控除」が使える
制度の詳細は、公式サイトがとても分かりやすいので参考にしてください:
👉 iDeCo公式サイト
iDeCoの掛け金の上限は人によって異なる
iDeCoでは、加入者の職業や企業年金の有無によって掛け金の上限が異なります。たとえば、
- 自営業者:月額68,000円まで
- 会社員(企業型DCなし):月額23,000円まで
- 会社員(企業型DCあり):月額20,000円または12,000円(条件による)
私は企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入しており、企業からの拠出額が月39,000円。
この場合、iDeCoで拠出できる上限は以下の計算式になります:
上限55,000円 − 企業型DC掛金39,000円 = iDeCo上限16,000円
よく分からない場合は、自分の勤務先の人事・労務担当者に確認しましょう。私も最初は分からず、会社に問い合わせて上限を確認しました。
【実体験】SBI証券でiDeCo口座を開設した手順
私は普段から積立NISAで使っているSBI証券でiDeCoも開設しました。その流れを一つひとつ紹介します。
① ポイントサイト経由で申し込み
SBI証券のサイトから直接申し込むことも可能ですが、ポイントサイト経由で申し込むとちょっとお得です。私は「Point Income」経由で申し込み、500円分のポイントをゲットしました。
ポイントサイト活用は、手間も少なく、リスクもないのでおすすめです。
② Webフォームに必要事項を入力
個人情報の入力に加え、以下の書類のアップロードが必要です:
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 事業所登録申請書兼第二号加入者に係る事業主の証明書
この「事業主の証明書」は勤務先に記入してもらう必要があるため、ここが最初のハードルです。私の会社では、登録事業者番号の記入漏れがあり、それに気づかずSBI証券にアップロードしてしまいました…。
しかも、一度アップロードした書類は自分で修正できないため、SBI証券のコールセンターに連絡し、個別対応してもらうことに。
この経験から言えるのは、「書類の内容は必ずダブルチェック」ということ。手戻りになると、時間も手間もかかります。
③ 投資信託の銘柄を選ぶ
iDeCoでは、どの商品(投資信託)に掛け金を投資するか自分で選ぶ必要があります。
私は積立NISAでは「eMAXIS Slim S&P500」を購入していたため、iDeCoでは分散を意識して「オールカントリー」にしようと思っていました。
しかし、SBI証券のiDeCo商品ラインナップを見て驚き…
なんと「オールカントリー(日本除く)」しかないのです!
オールカントリーのはずが「日本除く」って…ちょっと違和感ありましたが、他に良さそうな選択肢がなかったため、そのまま選びました。
④ 書類受領と初回引き落としまでの流れ
申込完了から約2か月後、以下の2点が郵送で届きました:
- 「iDeCo専用Webサイト」のログインIDとパスワード
- 「個人型年金加入確認通知書」
ただし、通知が遅かっただけで、実際の口座開設は申込月(9月)から始まっていたようで、初回は9〜10月分の2か月分が一括引き落とされていました。
iDeCoを始める際の注意点
- 掛け金の上限は職業・制度によって異なる
→ 自分の条件をきちんと把握しよう - 書類の不備に注意!
→ 勤務先に記入してもらう書類はダブルチェック必須 - 運用商品は慎重に選ぶ
→ 分散投資や信託報酬(手数料)も考慮して選びましょう
まとめ|iDeCoは手間もあるが、将来への強力な資産形成ツール!
SBI証券でのiDeCo口座開設は、手間に感じる部分もありましたが、実際にやってみると想像以上にシンプルでした。
節税効果が非常に高いため、特に年収が高めの会社員の方にはメリットが大きい制度です。
私は今後もiDeCoの運用成績や状況について定期的にブログで報告していく予定です。
ぜひ皆さんも、少しずつ老後に向けた資産形成をスタートしてみてはいかがでしょうか。

金融・投資ランキング
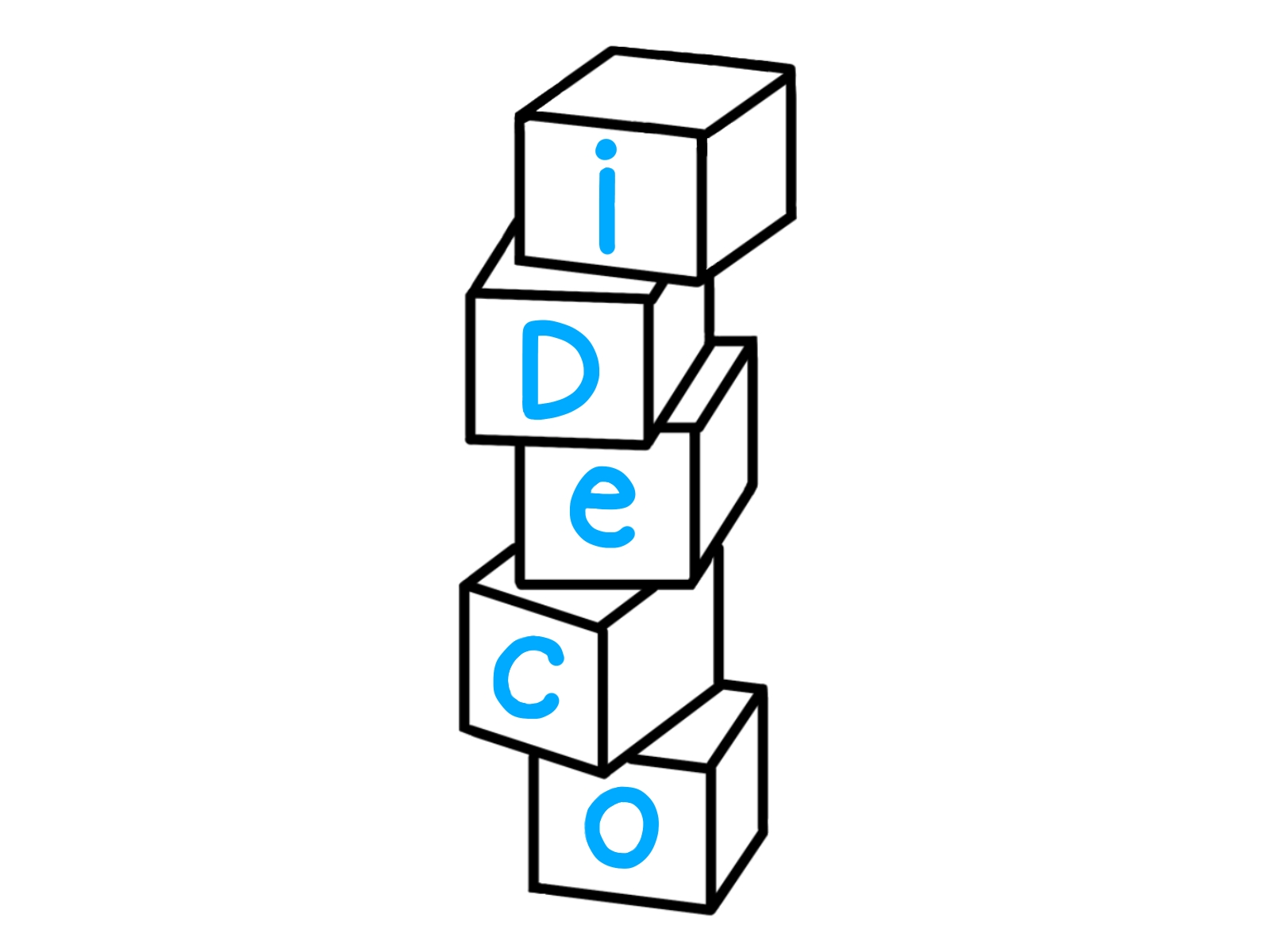


コメント