農地を相続したものの、自分で農業を続ける予定がなく、売却を検討するケースは少なくありません。しかし、畑や田んぼなどの農地を売却する際には、譲渡所得税がかかり、手続きも一般的な不動産売却とは異なる点が多くあります。こちらのブログでも紹介したとおり現在叔父の相続手続きを手伝っており、母が叔父の土地を相続し売却手続きを進める予定ですが、本記事では、相続した農地の売却に伴う譲渡所得税の考え方や、節税対策について詳しく解説します。
相続した農地の売却にかかる譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。これは、売却価格から取得費や諸経費を差し引いた譲渡所得に対して課税されるものです。
① 譲渡所得の計算式
譲渡所得は以下の計算式で求められます。
- 取得費:相続した農地の場合、被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぐ。ただし、不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とする。
- 譲渡費用:売却にかかった仲介手数料、測量費、登記費用など。
② 短期譲渡所得と長期譲渡所得
譲渡所得税率は、所有期間に応じて異なります。
- 短期譲渡所得(5年以下):税率 39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(5年超):税率 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
相続した場合、被相続人の所有期間を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得として扱われます。
相続した農地を売却する方法と税制優遇
農地の売却方法には、大きく分けて以下の2種類があります。
① 農地のまま売却(農地法3条許可)
農地をそのまま売却する場合、買主は農業を営む個人または法人である必要があります。この場合、農業委員会から農地法3条許可を取得しなければなりません。
税制優遇:
- 800万円の特別控除(条件付きで適用される可能性あり)
- 相続税納税猶予が継続可能(一定条件を満たす場合)
- 固定資産税が低く抑えられる(農地としての評価額が低いため)
ただし、買い手が見つかりにくく、売却までに時間がかかる可能性があります。
② 農地を転用して売却(農地法5条許可)
農地を宅地などに転用して売却する場合、農地法5条の許可が必要です。
税制優遇:
- 相続税の取得費加算の特例(相続税申告後3年以内の売却で取得費に相続税の一部を加算可能)
- 土地の評価が高くなり、高値で売れる可能性がある
ただし、農地転用には手続きや費用がかかるため、事前に調査が必要です。
節税対策のポイント
① 相続税の取得費加算の特例を活用する
相続税を支払った場合、売却時にその一部を取得費に加算できる制度があります。これにより譲渡所得を抑え、税負担を軽減できます。ただし相続税を支払うのは約8%というデータもあるように多くの方は対象外となりそうです。
適用条件:
- 相続税の申告期限(10ヶ月以内)から3年以内に売却すること
② ふるさと納税や他の控除を活用する
農地売却でまとまった譲渡所得が出た場合、ふるさと納税を活用することで住民税の負担を軽減できます。
また、医療費控除や小規模企業共済の掛金控除などを利用することで、所得税を抑えることも可能です。
③ 譲渡時期の調整
売却時期を調整し、譲渡所得が多くなりすぎないように分散することで、税率の影響を抑えることができます。
まとめ
- 相続した農地の売却には、譲渡所得税がかかるが、被相続人の所有期間を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得として扱われる。
- 農地の売却方法には、「農地のまま売却(農地法3条許可)」と「転用して売却(農地法5条許可)」の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがある。
- 節税対策として、「相続税の取得費加算」「ふるさと納税」「売却時期の調整」などを活用するのが有効。
農地の売却は通常の不動産売却とは異なるため、事前に農業委員会や税理士、不動産業者に相談しながら進めるのが重要です。
私も今後実際の売却に向けて色々と調整していきますので随時状況についてはアップしていきます。
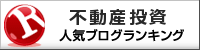
不動産投資ランキング



コメント