はじめに
高年収のサラリーマンは、一見すると経済的に恵まれているように思われますが、実は公的支援制度の多くで”所得制限の壁”に直面しています。
例えば、認可保育園の保育料は高額、配偶者控除は適用外、高校の授業料支援も受けられない…など、年収が上がるほど制度の対象から外されてしまいます。
しかし、不動産投資によって”赤字”を作り出し、損益通算で課税所得を圧縮することで、これらの制度が再び使えるようになる可能性があります。
本記事では、
- 所得制限のある制度一覧
- 不動産投資による損益通算の仕組み
- 制度が復活するシミュレーション
- 損益通算を行う際の注意点
を詳しく解説します。
所得制限によって制限される各種支援制度
認可保育園の保育料
保育料は自治体によって異なりますが、基本的に住民税課税額(=課税所得)に応じて段階的に設定されています。高年収家庭では月額5〜10万円近くに達することも。
課税所得を下げることで、1〜2階層下げられる場合、年間数十万円の節約が可能です。
高校就学支援金制度
私立高校を含む授業料支援制度で、目安として年収910万円未満(4人世帯)で月額最大3万3,000円の支援を受けられます。
高収入世帯ではこのラインをわずかに超えて対象外となることが多いですが、課税所得を調整すれば再び対象になる可能性があります。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除(38万円)は、納税者の合計所得が1,000万円を超えると適用不可となります。仮に年収1,100万円でも、不動産投資の赤字で課税所得を950万円に抑えることができれば、控除が復活します。
特別控除(最大38万円)も同様に、合計所得1,000〜1,100万円のゾーンで逓減される仕組みのため、損益通算による調整で大きな節税効果があります。
障害者支援制度
障害のある家族がいる場合、さまざまな支援制度がありますが、以下のようなものには所得制限があります。
特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の子どもを育てる家庭に支給される手当。支給額は障害の程度によりますが、所得制限で対象外になるケースが多いです。
自治体による医療費助成や交通支援
障害者手帳を持っていても、高年収の場合は助成対象外となる地域もあります。
自立支援医療(精神通院医療)制度
所得に応じて自己負担割合(1割〜3割)が変わります。
いずれも、課税所得を抑えることで、支援の対象に再び入れる可能性が生まれます。
不動産投資の赤字は給与所得と損益通算できる
損益通算とは?
不動産所得(家賃収入から経費を引いた金額)が赤字になった場合、その損失を給与所得など他の所得から差し引くことができます。これが”損益通算”です。
その結果、課税所得が減り、税金だけでなく、所得制限のある支援制度への影響も軽減されるのです。
赤字の作り方
- 減価償却費(建物部分)
- ローン利息(建物分)
- 修繕費、管理費、保険料など
これらを適切に計上すれば、キャッシュフローは黒字でも、帳簿上の赤字を作ることが可能です。
所得制限を回避して再び活用できる制度一覧
| 制度名 | 所得制限目安 | 損益通算の影響 |
|---|---|---|
| 保育料(認可) | 住民税課税額で区分 | 年間数十万円軽減可能 |
| 高校就学支援金 | 年収910万円未満 | 対象へ復帰の可能性 |
| 配偶者控除 | 合計所得1,000万円未満 | 控除最大38万円が復活 |
| 特別児童扶養手当 | 世帯年収950万円未満程度 | 支給対象復帰の可能性 |
| 障害者支援(自治体) | 住民税課税額で区分 | 医療費助成・交通支援などが対象に戻る |
損益通算を活用する際の注意点
土地部分の利息は対象外
損益通算できるのは建物部分の減価償却費や利息のみ。土地にかかる利息は対象外なので注意が必要です。
毎年の赤字は要注意
毎年恒常的に赤字申告を続けると、税務署に”節税目的の不適切な経費計上”と疑われる可能性があります。税理士と相談し、適切なバランスで行いましょう。
実際のキャッシュフローを重視
帳簿上の赤字であっても、実際のキャッシュフローが赤字では投資として失敗です。黒字運営の中で節税を狙うのがベストです。
まとめ:高年収層こそ戦略的に制度を活用せよ
不動産投資による損益通算は、単なる節税にとどまらず、今まで諦めていた各種制度の復活にもつながる強力な武器です。
高収入サラリーマンは、収入が高いがゆえに損している支援制度が数多く存在します。
制度を正しく理解し、損益通算という合法的な手段を活用することで、家計の最適化と資産形成を同時に進めることが可能です。
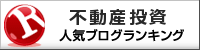
不動産投資ランキング
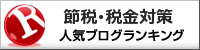
節税・税金対策ランキング
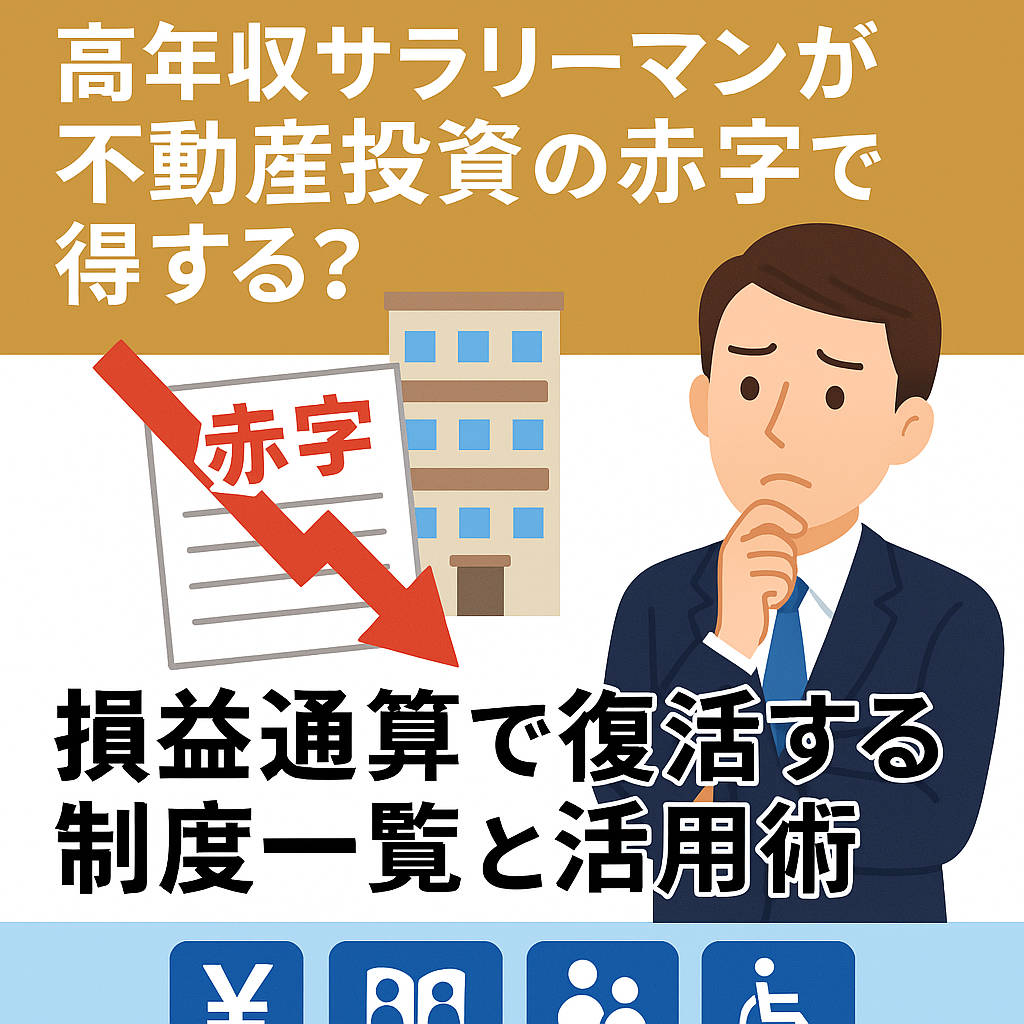


コメント