2024年に叔父が亡くなったことをきっかけに、私は母とともに相続手続きを進めてきました。以前の記事では、相続発生後の介護施設の退所手続きや初期対応についてまとめましたが(記事はこちら)、今回の帰省ではいよいよ遺産分割協議書の作成と相続関連書類の整備を本格的に進めました。
本記事では、相続人の確定という最大の難関と、農地相続における市役所と法務局の登記情報の違いについて、実体験に基づきながら詳しく紹介します。これから相続手続きを控えている方の参考になれば幸いです。
相続人の確定は「最初のステップ」であり「最大のハードル」
相続手続きの全体像については、以下の記事でもまとめています。
その中でも、最初にして最重要なステップが「相続人の確定」です。被相続人の遺産を誰が相続できるのかを法的に明確にするためには、戸籍謄本の収集が必要不可欠ですが、これが思った以上に難解でした。
出生から死亡までの戸籍が必要、だけでは終わらない
一般的には、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて揃える」ことで相続人を確定できるとされています。しかし実際には、取得した戸籍謄本から過去の改製原戸籍や除籍謄本が必要になるケースが多くあります。
今回もまさにそのパターンで、被相続人(叔父)の戸籍を取得したところ、
- 結婚前の戸籍
- 両親(被相続人の父・母)の死亡確認
- 親の結婚や離婚、再婚などの事実
などを裏付けるために、被相続人の母の出生から結婚まで、そして被相続人の父の死亡後から母の死亡までの戸籍も必要となりました。
古い戸籍は手書きで読解不能!?行政書士の力を借りるべし
古い戸籍は、手書きかつ旧漢字・変体仮名が多く、何が書かれているのかほとんど解読できません。今回、無料の相続相談を活用して行政書士の方に戸籍を確認してもらい、ようやく必要な追加書類が明確になりました。
専門家に見てもらうのが最短ルートです。
市区町村や法テラス、行政書士会などで行われている1時間程度の無料相談でも十分に役立つので、ぜひ活用することをおすすめします。
農地相続で気をつけたい「市役所と法務局の情報のズレ」
今回は農地も複数あり、その相続に関しても一筋縄ではいきませんでした。
まず最初に市役所で取得したのが「土地・家屋名寄帳兼課税台帳」でした。これは市町村が課税のために管理している土地・建物の一覧表です。しかし、実際の相続登記に必要なのは、法務局が管理している「不動産登記事項証明書(登記簿謄本)」です。
名寄帳と登記簿は微妙に違う!
市役所で発行された名寄帳を元に、遺産分割協議書の案を作成していたのですが、法務局で取得した登記事項証明書と照らし合わせたところ、地番や地目の記載、面積などに微妙な違いがあることが判明。
結局、法務局の登記情報に合わせて遺産分割協議書を作り直すことになりました。
遺産分割協議書の作成と関係者との調整
相続人が確定し、不動産や預貯金などの財産内容が明らかになったら、いよいよ遺産分割協議書の作成です。
今回は、
- 不動産(土地・建物)の分割方法
- 農地の分配
- 金融機関口座の引き継ぎ方法
などを全て明記しました。
事前に金融機関にも相談し、協議書の内容に問題がないかを確認。必要な添付書類(戸籍謄本、印鑑証明書、相続関係説明図など)も一式揃え、不動産登記申請書も作成済みです。
ここまでやれば、あとは提出するだけ
GW中の帰省でここまで作業を進め、あとは提出するだけの状態にまで整えました。書類提出や登記申請、金融機関での手続きは母と叔母にバトンタッチします。
私自身は今後もサポートは継続しつつも、ひとまず一段落。長かった相続手続きもようやく出口が見えてきました。
まとめ|相続手続きは「情報戦」でもある
相続人の確定には専門知識が必要で、農地のように登記情報と課税情報が一致しないことも多く、素人だけで完璧にやるのは難しいと痛感しました。専門家の無料相談を賢く使い、必要な情報を確実に揃えることが、スムーズな遺産分割と相続登記のカギになります。
相続関連のおすすめ記事

社会・経済ランキング
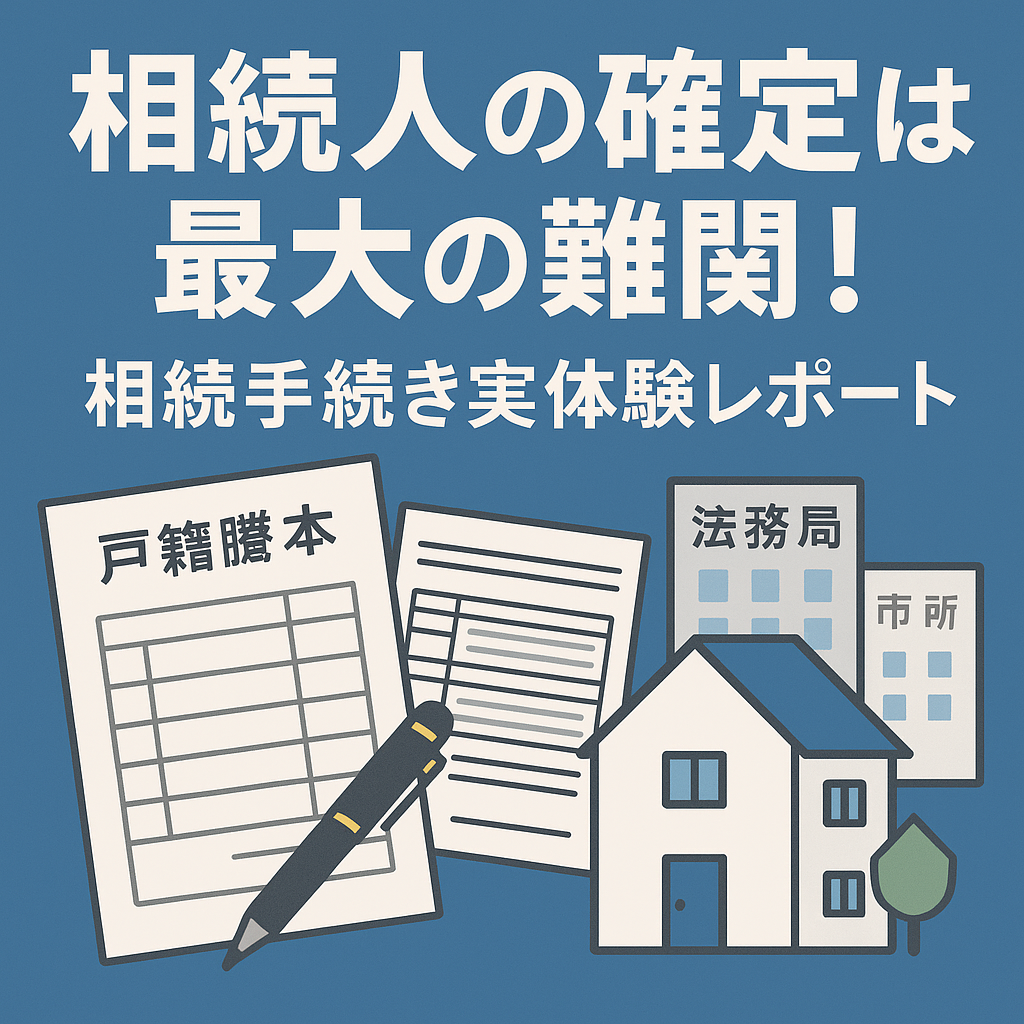


コメント