はじめに|農地売却を進める中で見えてきた課題
先日、叔父が保有していた農地の売却に向けて、不動産会社と専属専任媒介契約を結びました。初めての農地売却ということもあり、手探りの状態からのスタートです。
※こちらのブログで専属専任媒介契約スタートの内容はまとめています。
今回はその1週間後の進捗報告が不動産業者から届いたので、その内容を共有しつつ、思いがけず発覚した借主の存在についても整理していきたいと思います。農地売却を検討している方にとって、参考になるリアルな情報になれば幸いです。
専属専任媒介契約を結んで1週間|1件の問い合わせが発生
媒介契約を締結してから1週間、不動産会社より連絡がありました。
「現在、1件のお問い合わせがあり、こちらから買主候補の方へ提案中です」
とのこと。
専属専任媒介契約では、不動産会社から1週間に1回以上の活動報告が義務付けられているため、こうした小さな進展でも逐一共有してくれるのは安心感があります。
現段階ではまだ「興味あり」のレベルですが、農地という流動性の低い資産を売却する場合、このような小さな一歩が非常に重要になってきます。
想定外の事実:農地に2名の借主が存在していた
今回の売却を進めるにあたって、登記簿や関係者からの聞き取りを通じて、新たな事実が明らかになりました。
なんと、その農地には借主が2名いたのです。
借主①:叔父と口約束で契約、現金手渡しで年間賃料を支払っていた
1人目の借主は、叔父との口約束による年間契約で農地を利用していたようです。賃料は現金手渡しで支払っていたとのことですが、契約書や領収書などは存在しません。
このようなケースでは、「使用貸借か賃貸借か」の判断が難しく、売却後の明け渡しにも影響する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
借主②:氏名・連絡先は判明しているが、連絡が取れない
2人目の借主については、氏名・住所・電話番号は分かっているものの、現在は連絡が取れない状態です。
このままでは売却後のトラブルの火種となりかねないため、不動産会社とも連携しながら、できる限りの手段で接触を試みる方針です。
借主との関係整理が売却成功のカギ
農地に限らず、不動産に借主が存在する場合、その処遇が売却に大きく影響します。特に農地のように使用実態があいまいなケースでは、次のような対応が求められます。
- 借主との契約形態の確認(口約束でも賃貸借と認定されることがある)
- 使用期間や賃料、利用状況の把握
- 書面による合意の取得(可能ならば)
- 明け渡しの意思確認
借主との関係整理が不十分なまま売却を進めると、「買主が引き継がなければならない利用者」としてリスク評価され、価格交渉や売却延期に発展する恐れがあります。
今後の対応方針|一つ一つ丁寧に整理していく
今回の件で、農地の売却が想像以上に複雑であることを実感しました。特に相続した土地では、長年放置されていた利用実態や人間関係が絡んでくることが多いため、慎重に進める必要があります。
今後の方針としては、以下のような対応を考えています。
- 不動産会社と連携しながら、買主候補の動向を見守る
- 借主①とは、できる限り書面を交わし、現状の契約を明文化
- 借主②に関しては、再度連絡を試み、必要であれば行政や司法書士への相談も検討
まとめ|農地売却は一筋縄ではいかない。だからこそ、早めの行動が大切
今回、専属専任媒介契約を結んでからの1週間で、少しずつ状況が動き始めました。同時に、借主の存在という想定外の問題にも直面し、不動産売却の奥深さをあらためて実感しています。
農地や相続した土地の売却を考えている方には、「早めに動くことの大切さ」を強くお伝えしたいと思います。登記簿だけでなく、現地の利用実態や関係者との聞き取りも含めて、全体像を把握することが何よりの第一歩です。
今後も進捗があれば、引き続きこのブログで共有していきます。どうか、良い買主が見つかりますように──。
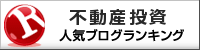
不動産投資ランキング

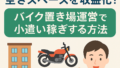
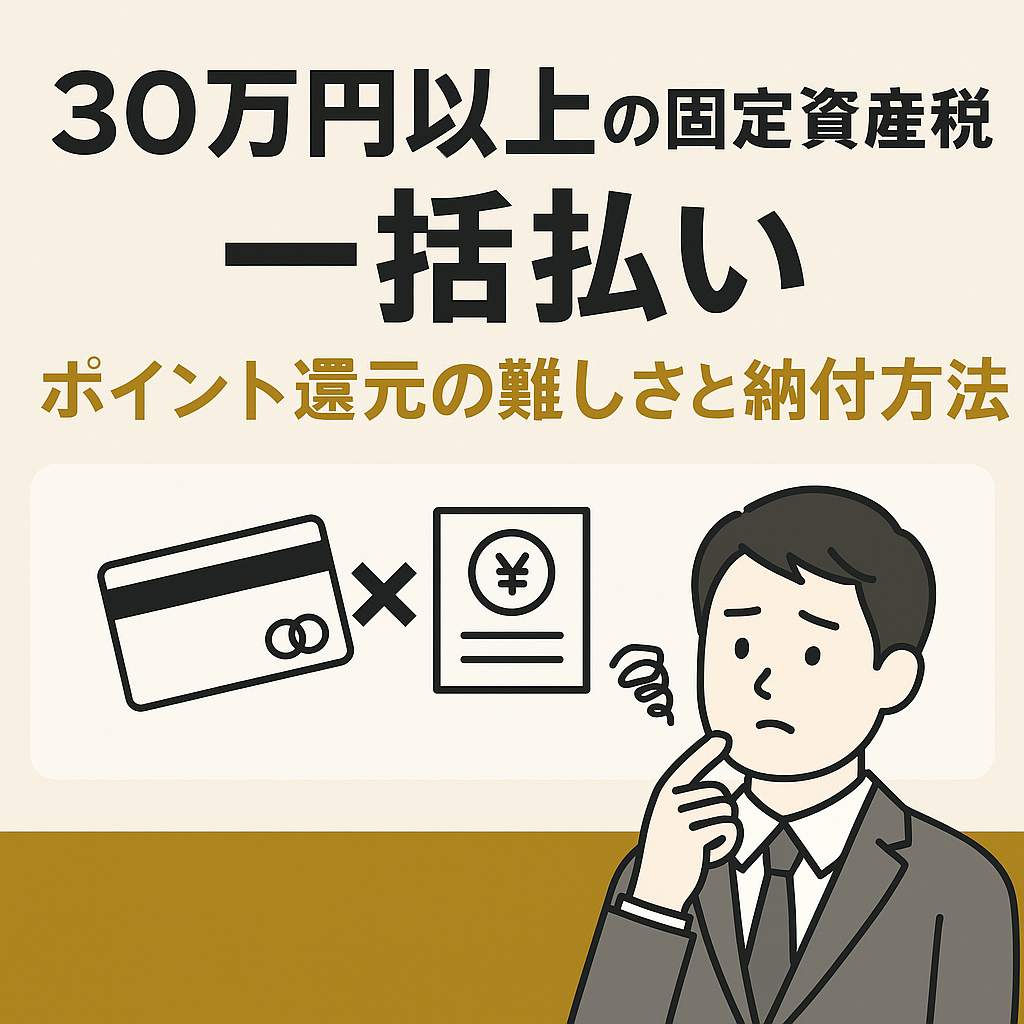
コメント