はじめに:農地の売却は「現地確認」がカギだった
相続した農地の売却手続きを進める中で、GWに帰省し現地調査を実施しました。
事前に「登記情報提供サービス」で地番を特定し、ある程度の目星をつけてから訪問しましたが、現地で次々と予想外の問題が発覚。
この記事では、農地売却を検討している方に向けて、現地調査の重要性と実際のトラブル・対応策を、リアルな体験をもとにお伝えします。
登記情報提供サービスで事前に地番を確認
売却対象の土地を調べるために活用したのが、「登記情報提供サービス」です。
住所や地図から地番を特定できるため、正確な場所の把握に非常に役立ちました。
➡ 登記情報提供サービスの詳細や使い方については、以下の記事で詳しく解説しています:
▶︎ 農地売却の準備と登記情報提供サービスの活用方法はこちら
【問題①】貸出中の農地が「名寄帳」に存在しない?
当初の情報では、2か所の農地を他者に貸出しているとのことでした。
ところが、名寄帳(固定資産の所有者一覧)には1か所しか記載されていません。
「もしかしてすでに売却済み?」という疑念が生じ、親族や周囲の方に聞き込みをした結果、売却はされていないことが判明。
【面会で判明】祖父名義のままの土地だった!
名寄帳になかった土地について、貸出している方に直接会って場所を特定。
その上で、地番を調べて有料の登記情報提供サービス(331円)で登記情報を取得したところ、衝撃の事実が明らかに。
なんとその土地は、昭和36年に亡くなった祖父の名義のままだったのです。
つまり、相続登記が長年未了だったという事実がここで発覚。
これは今後の相続登記義務(2024年4月施行)を考慮しても、対処必須の課題といえます。
【現状対応】貸主には現状維持でお願い
この土地は叔父の所有ではないため、今回は売却対象から外すことにしました。
貸出している方には当面の間、現状のままで管理を継続してもらうよう依頼。
正式な相続登記については、今後の検討課題として保留としています。
【問題②】田舎の農地は売却相場が極端に低い
もう一方の農地では、貸出している農家の方と面会し、売却の意向を伝えました。
そこで聞いたのが、「相場は不動産会社の1/5~1/8くらいでは?」という話。
地元の実需者感覚と不動産会社の査定には、大きな乖離があることがわかりました。
現実として、田舎の農地は買い手が少なく、売却価格も非常に安価になる傾向があります。
この情報を不動産会社にも共有し、改めて売却戦略を検討する方針としました。
【問題③】売却予定の農地が“通路”になっていた!
さらに現地調査で新たに判明したのが、叔母が相続する予定の居宅が道路に面していないという事実。
居宅の前面の農地は売却予定でしたが、その土地を通らなければ道路に出られない構造だったのです。
つまり、農地を売ってしまうと、叔母が家から出られなくなる事態に。
【対策】売却時に「通行許可」の条件を明記
この問題に対しては、不動産会社と相談の上、売却時に「通行利用を許可する」条件を付けることで対処することにしました。
これは、いわゆる**「通行地役権」や「使用貸借」のような形**での合意を目指すものです。
売却後のトラブル防止のためにも、こうした条件の明示は非常に重要です。
現地を見て初めて分かる「農地売却の現実」
今回の経験を通じて痛感したのは、「農地売却は机上では完結しない」という事実。
- 名寄帳に載っていない土地の存在
- 祖父名義のまま放置された農地
- 通行・道路接道に関する重大な制約
- 不動産会社の査定と地元感覚との乖離
どれも現地を実際に訪れなければ分からなかったことばかりでした。
まとめ:農地売却は「柔軟な対応」と「時間の確保」が重要
農地売却は、一筋縄ではいきません。
特に相続した土地では、登記・名義・接道・価格など、あらゆる問題が絡んできます。
今回の体験から学んだことは以下の通りです。
✅ 登記情報や名寄帳をもとに、必ず現地調査を行うこと
✅ 貸出先や地元住民との面会で実態を把握すること
✅ 価格査定はあくまで参考、現地相場感覚を知ること
✅ 通行権やインフラ面に注意し、条件付き売却を検討すること
今後も売却を進めながら、必要な情報収集と対応を続けていきます。
農地の相続や売却で悩んでいる方にとって、少しでも役立つ体験談となれば幸いです。
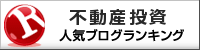
不動産投資ランキング

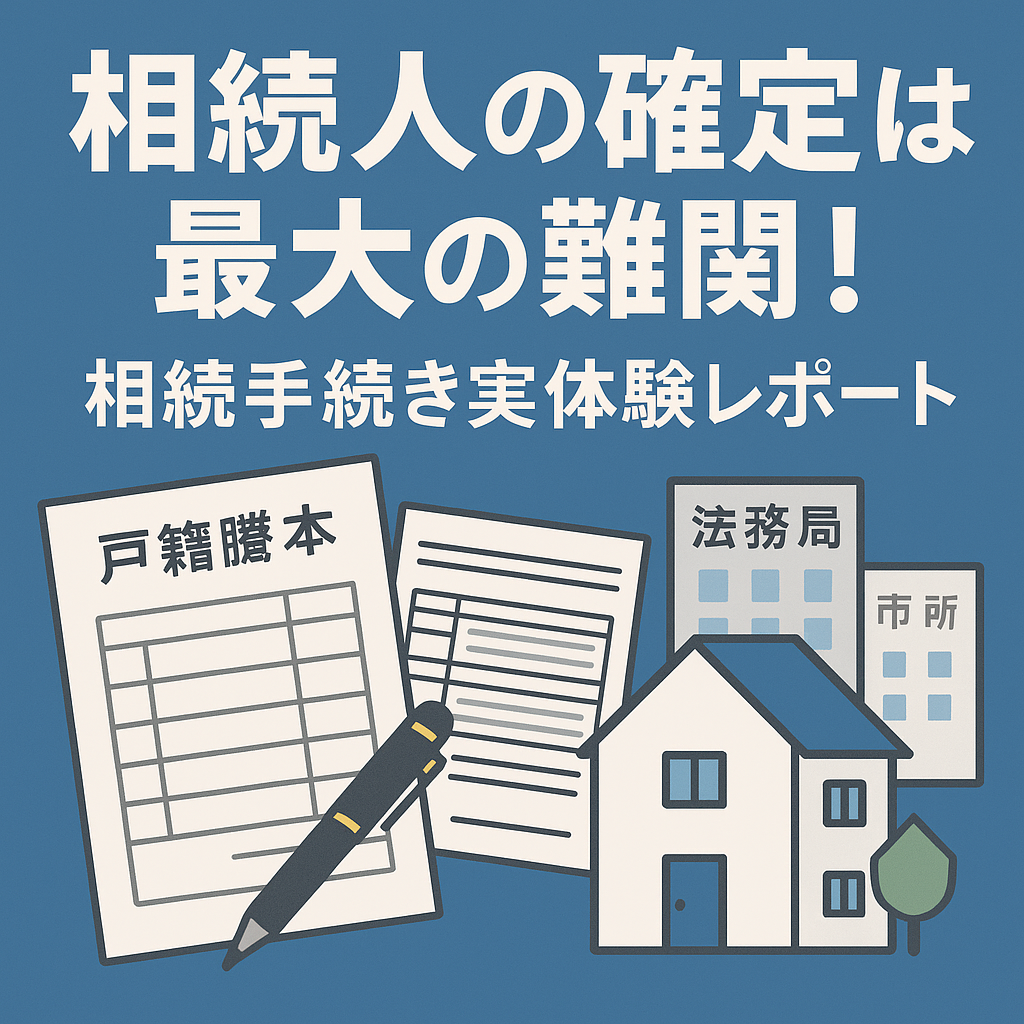
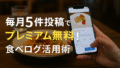
コメント